ここ数年、詐欺の被害がかつてないほど急増していることをご存じでしょうか。
以下は警察庁が発表している、詐欺の認知件数や被害額をまとめた資料です。
出典:
警察庁「令和6年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について(確定値版)」(https://www.npa.go.jp/bureau/criminal/souni/tokusyusagi/hurikomesagi_toukei2024.pdf)
この資料によると、2024年の特殊詐欺による被害額は717億円を超えており、これは1日あたり約2億円がだまし取られている計算になります。しかも、手口は年々巧妙化しています。
おそらく多くの方が、不審な電話やメッセージを受け取った経験があるのではないでしょうか。もはや詐欺はニュースの中の出来事ではなく、私たちの身近な生活の中にまで忍び寄ってきています。
警察や金融庁のウェブサイトには、詐欺の具体的な手口や対策が詳しく紹介されています。
出典:
警察庁「安全・安心のまちづくり」(https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/)
このように、具体的な事例や注意点はさまざまなところで紹介されていますが、私が特に注目したいのは「詐欺に遭わないためのマインドセット」です。
多くの被害事例を見ていく中で、詐欺に遭った方々がだまされてしまった原因は、単に対策を知らなかったからではなく、日頃の考え方や心構えそのものに原因があるのではないかと感じるようになりました。
今回は、詐欺にだまされないために必要な「マインドセット」や「ものの見方」に焦点を当てて、お話ししていきます。
相手から来るものは全部詐欺と思うべき
この見出しは、あえて極端な表現を使っていますが、近年の詐欺や詐欺まがいの勧誘が急増していることを考えると、
「相手から寄ってくるものはすべて詐欺」くらいの心構えがちょうどいいと考えています。
たとえ詐欺でなくても、その大半は詐欺まがいの商品や、割高で不要な営業です。
優良企業は押し売りしない
なぜそう言い切れるのかというと、本当に優れた商品やサービスに、強引な営業は必要ないからです。
たとえば、あなたはこれまでに
- トヨタ自動車からしつこく営業を受けたことがあるでしょうか?
- メガバンクから「口座を作ってください」と何度も電話がかかってきたことは?
- 大手家電メーカーがショッピングモールで声をかけ、商品を押し売りしてきたことはありましたか?
こうした企業は、無理に売り込まなくても、信頼や実績で自然に選ばれています。
もちろん、テレビCMなどの広告はありますが、
強引でしつこい勧誘は、むしろ企業イメージを損なうだけです。
まともな企業ほど、そんな手法は使いません。
強引なセールスや執拗な勧誘は法的リスクが高い
以下のような行為は、すべて特定商取引法に抵触する可能性があります。
- 威圧的な言動による契約の強要
- 「今契約しないと損をする」などの過度な煽り文句
- 一度断った相手への繰り返し勧誘
- 虚偽の説明や、重要事項を意図的に説明しない行為
- 「勧誘ではない」と見せかけて呼び出し、実際には勧誘を行う行為
これらの行為を行った企業には、業務停止命令や刑事罰の対象になる可能性があります。
つまり、しつこく電話をかけてきたり、路上で声をかけてきたりするような勧誘は、企業にとって非常にリスクが高い行為のはずなのです。
なぜ相手から寄ってくるのか?
このように、強引かつ執拗な勧誘は、法的にも企業イメージとしてもリスクが大きいはずです。
普通に考えれば、そんなことをしている企業には、誰も関わりたくないと思うでしょう。
それでもなぜ、彼らはあなたに寄ってくるのか。
答えはシンプルです。
そうでもしなければ売れない、買ってもらえない商品やサービスだからです。
不動産投資の勧誘

「不動産投資をしてみませんか?今、いいマンションがあるんですよ〜」
こんな誘いを受けたことはありませんか?
もしその物件が本当に投資価値のある優良物件なら、すでにプロの投資家が目を光らせているはずで、一般人にまで情報が下りてくること自体がおかしいのです。
そんなに優良な商品が、たまたま売れ残って、一般人に声をかけて売られているなんて、おかしな話です。仮に“たまたま”存在したとしても、なぜそれが、あなたの元に偶然舞い込んでくるのでしょうか?
答えは明白です。
十中八九、それは儲からないどころか、赤字になり借金を背負うことになる物件だからです。
SNS経由の副業・ビジネス勧誘

- 「稼げる方法を教えます」
- 「一緒にビジネスしませんか?」
- 「プロフィール見てすごいと思いました!」
こうしたSNSのいきなりのDMも要注意です。
本当に稼げる方法があるのなら、なぜわざわざ赤の他人であるあなたに教える必要があるのでしょうか?できればライバルは作りたくないですし、普通は、家族や親しい友人などにしか教えたくないはずです。
仮に人手が必要だとしても、正規の手段で求人を出せば応募は集まるはずです。
それにも関わらず、なぜ一般的な求人媒体(ハローワーク、求人誌、企業サイトなど)を通さずに、SNSで直接募集をかけたり、他人に1通ずつDMを送るなどという効率の悪いことをするのでしょうか。
答えは簡単です。
公には募集できない内容、つまり詐欺まがいの案件だからです。
不要なものほど熱心に売り込まれる

- 「ウォーターサーバーを設置しませんか?」
- 「太陽光パネルと蓄電池で電気代が無料になりますよ!」
これらは、不要な商品の典型例です。
日本の水道水は、味の好みは別としても、安全に飲むことができます。
たとえば赤ちゃんのいる家庭等、一部の家庭では便利かもしれませんが、ほとんどの人にとっては不要です。
だからこそ、積極的な勧誘が行われているのです。
太陽光パネルと蓄電池の話も同様です。
本当に電気代が0円になるなら、すぐに口コミで広まり、戸建ての家庭がこぞって導入しているはずですよね?
しかし現実には、天候不順や夜間の消費、季節による発電量の変動があるため、電気代が完全に0になるケースは非常に少ないです。
設備の導入費用やメンテナンス費用、蓄電池の寿命なども考慮すると、むしろ損をする可能性すらあるのです。
仮に得をする場合でも、十分な勉強とリサーチが必要で、元を取るまでに10年以上かかることもあります。
調べれば調べるほど「不要な買い物」だと分かるのです。
外貨建て保険などの金融勧誘

- 「外貨建ての積立保険を始めてみませんか?」
- 「最近、円安が不安ですよね」
- 「老後の資産形成に最適です!」
このようなフレーズでの保険商品の勧誘も要注意です。
本当に魅力的な金融商品であれば、こんなにしつこく勧誘されることはありません。
たとえば――
- トヨタやAppleの株を「買いませんか?」と勧誘されたことはありますか?
- 銀行の定期預金をしつこく勧められたことは?
預金・株・債券も金融商品ですが、勧誘しなくても人は自然に使っています。
一方、外貨建ての積立保険などは、仕組みが複雑でコストが高く、リスクもあるのにあまり儲からない商品です。
だからこそ、必死に営業しないと売れないのです。
実際、金融庁も注意喚起を行っています。
出典:金融庁ウェブサイト「リスク性金融商品の販売会社等による顧客本位の業務運営に関するモニタリング結果」(https://www.fsa.go.jp/news/r5/kokyakuhoni/202403/01.pdf)
出典:金融庁ウェブサイト「外貨建保険販売の際の情報提供のあり方について」(https://www.fsa.go.jp/common/ronten/202003/02.pdf)
本当に優良な商品であれば、金融庁から注意されるようなことはありませんし、勧誘しなくても自然と加入者が集まるはずです。
対策:話を「聞かない」ことが最も有効
では、こうした勧誘にどう対処すればよいのでしょうか。
まず大前提として、相手から近づいてきた場合は一切取り合わないことが重要です。
たとえば職場などで保険の営業に声をかけられたら、「必要ありません」ときっぱり言いましょう。
先ほど特定商取引法の部分でも触れましたが、一度断ったにもかかわらず勧誘を続ける行為は違法です。
もし相手がしつこく食い下がってくるようなら、

「再勧誘の禁止ってご存じですか? 御社にクレームを入れますよ。」
と、一言伝えてみてください。
まともな会社・営業であれば必ず引き下がるはずです。
それでも引き下がらない営業がいれば、その人やその会社は明らかに異常です。絶対に話を聞いてはいけません。場合によっては警察を呼ぶことも検討してください。
また、ショッピングモールや街中で声をかけてくるタイプの勧誘には、完全に無視を決め込むのが最も有効です。
「無視するのは悪い気がする…」というこちらの善意に、相手は付け込んでくるのです。
安心してください。彼らは1日に何百人にも無視されていますので、気にしていません。
電話営業には一切応じない
電話営業への対策としては、知らない番号からの着信に出ないことです。
これは勧誘だけでなく、振り込め詐欺やなりすまし詐欺の初動である可能性もあるため、警戒しすぎるくらいでちょうどいいのです。
また、相手はプロです。最初は疑いながら話を聞いていても、
- 「あれ? これは本当かも」
- 「この商品は優良かも」
と思わせてしまうような高度な会話テクニックを持っています。そのため、基本的には話を聞かないことが最も重要です。
知識がある人ほど騙されやすいことも
ここまで読んで、金融リテラシーや知識がある人の中には
「自分はリテラシーが高いから騙されない」と感じた方もいるかもしれません。
確かに、不動産の知識があれば、賃貸業として成り立たない利回りの物件や空室リスクの高い物件は避けられるでしょうし、
金融知識があれば、過度に高い利回りを謳う仮想通貨系の複雑な投資商品は掴まないかもしれません。
しかし、「知識がある」ということは裏を返せば、
自分の知識と“整合性が取れてしまう案件”に対して、「これは大丈夫だ」と思い込んでしまう危うさもあるのです。
一度信じてしまうと、他者から「それ、危ないんじゃない?」と言われても、
「いや、これは〇〇だから大丈夫なんだよ」ともっともらしい説明ができてしまい、周囲がブレーキをかけられなくなります。
そして実際には、購入した不動産の近くで学校の移転が決まっており、数年後には全く入居者がいなくなる…
あるいは、「オルタナティブ資産として分散投資になる」と思って投資した商品が、実は運用実態がなく大きな損失を生む…
知識がある人ほど、時に大きな失敗をするリスクがあるのです。
まとめ:受け身の話はすべて警戒せよ
本当に価値のある情報や商品は、自分で調べて、自分で選び、自分で動いて手に入れるものです。
相手から持ち込まれる“うまい話”で得をするなんて甘いことはあり得ないのです。
- 向こうから来た話は断る
- 「自分は大丈夫」という慢心が一番危ない
- 知識の有無よりも、受け身かどうかがリスクの分かれ目
この3つを忘れずに、詐欺や不必要な勧誘から身を守っていきましょう。
今後も、詐欺に引っかからないためのマインドセットを発信していこうと思います。
ぜひ他の記事もご覧ください。
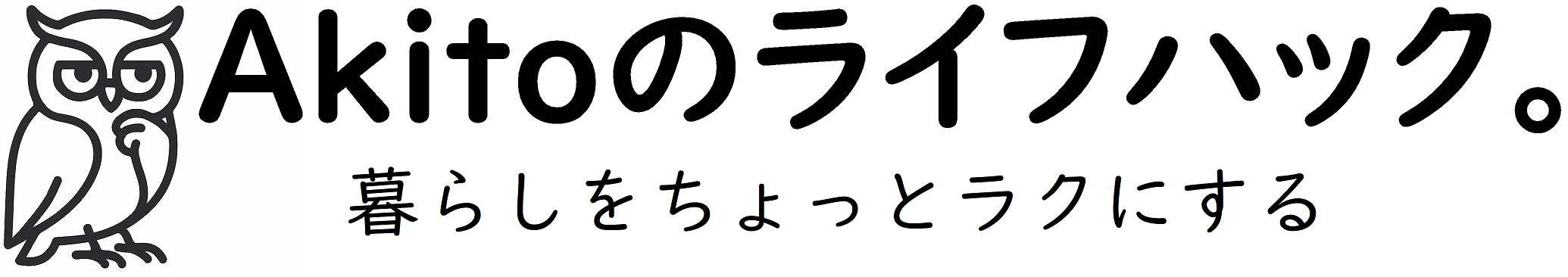


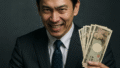
コメント