前回の記事では、「いい話は向こうからはやってこない」という話をしました。
本当に価値あるものは、自分で調べて、自分で判断し、自分で動かない限り、手に入れることはできないのです。
今回のテーマは、さらに根深いものです。
「他人の善意には裏がある」。
これは決して偏見ではありません。詐欺や詐欺まがいの商品は、多くが「善意を装った言葉」から始まります。
本当にあなたのことを思っている親や兄弟ですら、安易に信用すべきではありません。
なぜなら、彼ら自身がだまされているというケースも多くあるからです。
その落とし穴を象徴するエピソードを紹介します。
【信頼は罠にもなる】
地方で公務員として働いていたAさんは、兄から「今話題の仮想通貨に投資しないか」と誘われました。
兄はすでに数百万円を投資し、配当も得ていると語り、セミナーへの参加を強く勧めてきました。
Aさんは最初こそ疑ったものの、「兄が言うなら」と会場へ足を運び、話を聞いた末に、最終的に300万円を投資してしまいました。
しかし翌月、連絡先は不通、サイトは閉鎖。
ニュースでそれが「仮想通貨詐欺」だったことを知りました。
兄も騙されていたのです。配当に見えたお金は、自分の出資金の一部が“還元”されただけのもの。
典型的な「ポンジスキーム」と呼ばれる詐欺の手法でした。
兄は「加害者」ではなく、騙されたまま弟に勧めてしまった「被害者兼伝達者」でした。
ここで重要なのは、兄は善意で勧めていたという点です。
それでも、結果としてAさんは多額の損失を被り、兄弟の信頼関係にも大きな亀裂が入りました。
親切な人ほど疑え
他人からの善意など言語道断。
親兄弟ですら100%信用すべきでないのですから、他人などもってのほかです。
どんなに良い人に見えても、どんなにお世話になったとしても、他人が善意であなたに何かしてくれることは、99%ないと思うべきです。
「あなたにとって良いことをしてくれる」ということは、どこかに必ず相手にとって得になる仕組みがあるはずであり、
その“得”が、あなたにとっての“損”になりうるのです。
実際に、善意を装った詐欺は数多く存在します。
【祖母にかかってきた電話】
これは実際に私の祖母にかかってきた電話の話です。

「過払い金が戻ってきますよ。一度お話だけでもお聞かせ願えませんか」
といったものでした。
これを真に受けた祖母は、実際にオフィスビルに行こうとしていたのです。
後からわかったことですが、その業者は主に高齢者をターゲットにオフィスへ呼びつけ、
「過払い金が戻ってくる」と説明したうえで、手付金として数十万円をだまし取っていたのです。
さらに、偽名や架空法人名で借りたオフィスを数か月後に引き払い、連絡が取れなくなるという手口でした。
本来、過払い金は2010年6月以前に、カードキャッシングやカードローン、消費者金融などで15〜20%を超える高金利で借りていた場合に発生するものです。
そのため、銀行の住宅ローンや自動車ローン、あるいはショッピング目的のクレジットカードには関係ないんです。
にもかかわらず、「過払い金を取り戻すお手伝いをします」と近づき、優しく丁寧に高齢者の話を聞いて信用させ、最終的には金銭を奪うのです。
【いい人が勧誘してくるマルチ商法】
善意を装って近づいてくる存在には、他にもあります。いわゆる「マルチ商法」や「ねずみ講」と呼ばれる類のものです。
最近の「マルチ商法」はメディアなどの影響で名前の印象が悪くなってしまったため、「マルチレベルマーケティング(MLM)」や「ネットワークビジネス」などと名乗り勧誘しているようですが、基本的にはマルチ商法と同じものです。
SNSで知らない人から連絡が来るケース、友人からの紹介で始まるケース、最近ではマッチングアプリで知り合った人をきっかけに始まるケースも増えています。

「一緒に成功しよう!」
「○○さんには幸せになってほしいから」
こういった前向きで魅力的な言葉と、和やかな雰囲気で勧誘されるのが特徴です。
一見すると本当に“いい人”に見えることも多く、「こんなに親切な人がだますなんて信じられない」と感じるケースも少なくありません。
これは勧誘する側の話術が巧みな場合もありますが、実際には勧誘している本人も信じ込んでおり、
- 「これは本当にいいものだから」
- 「きっと成功できるはず」
と信じて動いていることもあり、より厄介です。
実際にあったマルチの経験
私自身も、以前に短期間お付き合いしていた女性が、マルチ商法の会社から化粧品を購入していたことがありました。
LINEのやりとりが頻繁だったため気になって「誰とLINEしてるの?」と聞いたところ、友人に紹介された販売員の方で、その人から化粧品を購入したとのことでした。
少し不審に思い、その会社名を聞いて調べてみると、やはりマルチ商法の企業でした。
販売員はLINEで、
- 「使用感はどうか?」
- 「他に肌悩みはないか?」
など、非常に丁寧にサポートしてくれていたようです。
購入後も親身になってくれるなんて、確かに“いい人”に見えるかもしれません。
ですが、この「いい人」こそが、注意すべき存在なのです。
こんなに親切にしてくれるのは、
- 「ほかにも商品を買わせよう」
- 「リピートしてもらおう」
- 「自分同様、販売員になってもらおう」
こういった思惑があるからなのです。
ここで、前回お伝えした「いい話は向こうからやってこない」という原則を思い出してください。
本当に良い商品であれば、話題になり、ドラッグストアや通販などで自然に販売されているはずです。
確かに、現在は通販サイトでも販売されているマルチ系の商品もありますが、本当に良い商品ならそれだけで十分で、わざわざ特定商取引法に触れるリスクや企業イメージを下げるリスクを冒して、販売員を通じて売る必要などありません。
つまり、製品そのものが大して良くない、あるいは品質は良くても価格が不相応に高いなど、消費者にとってあまりメリットのない商品である可能性が高いのです。
挙句の果てに、販売員として活動するようになると、多くの時間を浪費してしまうことになりかねません。
マルチ商法は、ねずみ講とは違い、法律上は違法ではありません。
しかし、大きく稼ぐのは非常に難しく、現実的に成功している人はごく一部です。
わざわざ販売員になるくらいなら、一般的な企業で働く方がずっと安定して収入を得られるはずです。
ホワイトに見えるものでも要注意
今までご紹介してきたのは違法性が高かったり、グレーなものでしたが、誰もが安心してしまうようなホワイトに見えるものでも、実際には大きなリスクを孕んでいる場合があります。
これらは社会的にも表向きの信用があり、一見まともに見えるため、非常に厄介です。
銀行窓口の金融商品
大手銀行や地方銀行、信用金庫などでは、名称は多少異なりますが、いずれも「資産運用」や「投資」に関する専用カウンターが設置されています。
「資産運用相談窓口」
「投資相談窓口」
「個人資産相談窓口」
などの名前を目にしたことがある方もいるのではないでしょうか。
普通に預金や手続きで窓口を訪れた際、担当者が通帳の残高や取引履歴を見ながら、

「このお金、何か使う予定はありますか?」
などと声をかけてきます。
そして雑談の中で、将来の不安や銀行預金の金利の低さなどを提示し、

「最近、資産運用を始める方が増えていますよ」
「NISAって聞いたことありませんか?国も推奨してるんですよ」
などと巧みに誘導してきます。
買わされるのはぼったくり商品
そして資産運用窓口に案内されると、不要な高コストの投資信託などを買わされてしまうのです。
銀行で販売される投資信託の多くは、アクティブファンドと呼ばれる手数料が高い商品です。
必ず損をするとは限りませんが、元本保証がない投資商品である以上、当然リスクがあります。リスクの割に手数料が高く、運用成績も芳しくない、簡単に言えば「ぼったくり商品」なのです。
高齢者にまで売ろうとする実態
私も以前、地元の地方銀行で、どう見ても80代くらいのおばあちゃんが「資産運用相談窓口」に案内されているのを目にしたことがあります。
はっきり言って、高齢者であれば、そもそも投資は必要ないことが多いでしょう。特に資産家でもなければ、なおさらです。
なぜなら、資産運用は時間を味方につけて長期的に利益を出すものだからです。
このような現場を見ると、銀行の闇を感じずにはいられませんでした。
電話での勧誘もあります
私の妻のもとにも銀行から電話がかかってきたことがあります。

「資産運用に興味はございませんか?」
と。
私が以前このブログで「地銀やメガバンクは解約すべき」と述べた理由の一つが、まさにここにあります。こんな高コストのぼったくり投資商品の営業の電話を掛けられたのではたまったものではありません。
投資信託で資産が半分になったというような大損は少ないかもしれませんが、元本割れリスクは当然ありますし、信用の高い銀行だからこそ警戒されにくいという点を考えると、非常に悪質に思えます。
保険の金融商品
前回の記事でも取り上げた、保険を使った金融商品についてです。
特に外貨建て積立保険のリスクについてはすでにお伝えしましたが、それ以外にも学資保険や養老保険など、投資型の商品は数多く存在します。
これらは「貯蓄型保険」と呼ばれることもありますが、実際には保険会社が契約者から預かったお金を運用し、その利益のごく一部だけを契約者に還元するという仕組みで、投資的性格が強い商品です。
本記事では詳細な商品分析は割愛しますが、こうした商品は多くの場合で非常に高い手数料が設定されており、実際に得られるリターンはごくわずかです。
さらに、途中解約すると元本割れするケースがほとんどです。
満期まで持ち続ければ元本は保証されるかもしれませんが、長期間にわたって資金が拘束される割にリターンが少ないため、投資商品としては“ぼったくり”に近い構造となっています。
それにも関わらず、
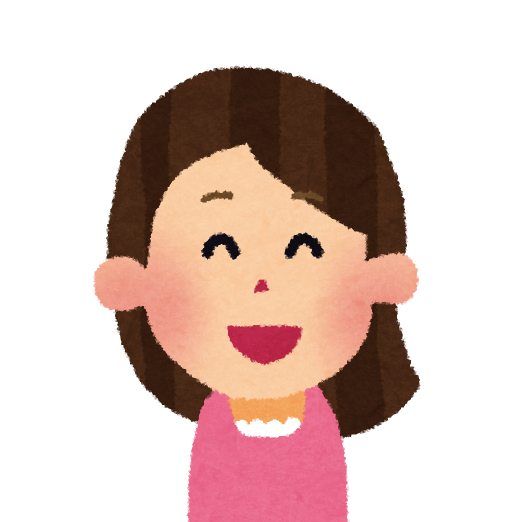
「預金だと全然増えませんよね」
「お子さんの教育費、今から不安じゃないですか?」
「死亡保障と貯蓄、どちらも備えられるから将来安心ですよ」
などと、もっともらしい言葉で勧誘してきます。
まとめ:他人の善意には裏がある
本記事でお伝えしたかったのは、「親切そうに見える人」ほど疑う視点を持つことの重要性です。
祖母に届いた丁寧な電話、友人の善意から始まったマルチ商法、そして銀行や保険会社による正当な顔をした営業行為――どれもが「善意の仮面」をかぶり、私たちの判断力を鈍らせます。
本当にあなたのためを思う他人など、現実にはほとんど存在しません。もしあるとすれば、その背景には必ず「相手にとっての得」があると考えるべきです。
本当に優れた商品やサービスであれば、押し売りや勧誘などしなくても自然に広がっているはずです。
「なぜこの人は、ここまで親切にするのか?」
その問いを常に心に置くことが、詐欺や損失を回避する第一歩になります。
冷静な疑いこそが、現代社会における最強の防犯意識です。
今後も、詐欺に引っかからないためのマインドセットを発信していこうと思います。
ぜひ他の記事もご覧ください。
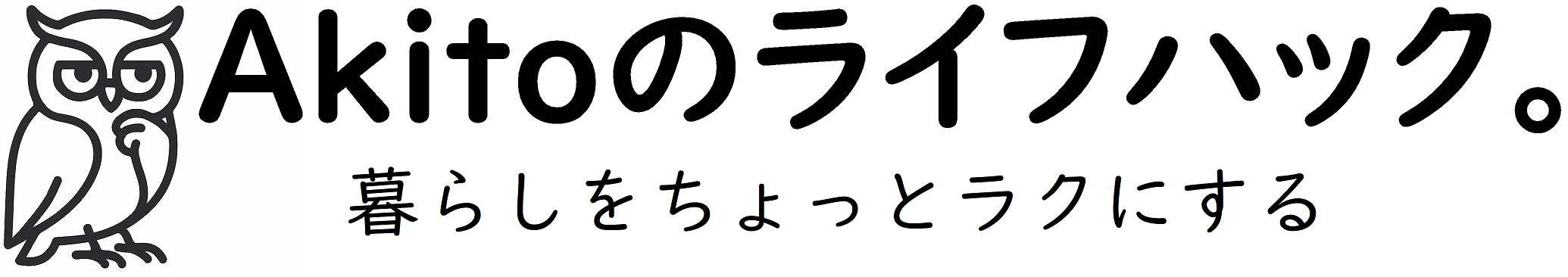

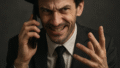

コメント