はじめに
近年、保険会社はさまざまなタイプの保険商品を販売しています。
自動車保険、火災保険、生命保険などは多くの人にとって身近な存在ですが、
中には「保険なのにお金が貯まる」とされる”貯蓄型保険“と呼ばれるものもあります。
これは、保障に加えて支払った保険料が将来的に戻ってきたり、”資産が増える”ことを売りにした商品です。
営業トークでは「将来の安心」「お金が戻る」といった言葉で不安をあおりながら、まるで得をするように見せていますが、実際には多くのリスクが潜む金融商品です。
この記事では、そうした貯蓄型保険のリスクや構造の実態について解説していきます。
貯蓄型保険とは?
貯蓄型保険とは、保険と資産運用がセットになった商品のことです。
主な商品例は以下の通りです。
- 外貨建て保険
- 養老保険
- 学資保険
- 個人年金保険
- 変額保険
これらは掛け捨て型の保険とは違い、満期まで契約し続けると、支払った保険料がそのまま戻ってきたり、運用され増えて戻ってくる可能性もあります。
例えば養老保険の場合、死亡したときには保険金が支払われますが、満期まで死亡しなければ、支払った金額の90%~100%以上が戻ってくることもあります。
そのため、「保険にも入れて、資産も増えるなんてお得そうだ」という印象を持たれがちです。
しかし実際には、これら貯蓄型保険の保険部分の保障は非常に少なく、貯蓄部分にも様々なリスクが潜んでいます。
元本割れリスク
「貯蓄型」と聞くと、多くの人は「貯金のようにお金が戻ってくる」とイメージします。
しかし、現実の貯蓄型保険では、支払った保険料よりも少ない金額しか返ってこない=元本割れが起こるリスクが常に付きまといます。
では、どういった場合に元本割れが起きるのでしょうか。
為替変動
外貨建て保険は、円で支払った保険料が米ドルや豪ドルなど外貨で運用される商品です。
例えば、契約時に「1ドル=150円」だったとしても、満期時に「1ドル=100円」になっていれば、同じドル建ての保険金を受け取っても円換算では大きく目減りしてしまいます。
しかも、信託報酬や各種手数料、為替手数料などが通常より高く設定されていることが多く、為替の変動次第では資産が大きく減ってしまう可能性があるのです。
途中解約
基本的に貯蓄型保険は途中解約時には支払い額の満額をもらうことができません。
契約から数年間は「解約控除」や「初期手数料」が大きく引かれる仕組みになっており、
途中解約した場合に大きく元本割れする仕組みになっています。
例えば10年契約の保険を3年で解約した場合、戻ってくる金額は支払額の50%程度ということも珍しくありません。
これは、保険会社が初期費用として多額の手数料を差し引いているからです。
長期間契約しても元本を超えないことがある
満期まで契約を続けても、受け取れる返戻金が支払った保険料の総額を上回らないことがあります。
商品によっては、満期時になってようやく「元が取れる」、あるいは数%しか増えていないケースもあるのです。
これは、低リスクな預金や国債と比べても、極端にリターンが低いことを意味します。
つまり「貯蓄」と名がついていても、実際には損をする可能性があることを認識しておく必要があります。
※こうした損失の背景にはどのような構造があるのか ― それについては次の「運用リスク」で詳しく解説します。
資金拘束リスク
先ほどご説明した通り、多くの貯蓄型保険は途中解約で大きく元本割れする仕組みです。
そのため、仮に「満期まで持ち続ければ全額戻ってくるタイプの保険」であっても、例えば10年契約なら10年間はそのお金を自由に使えません。
突発的な事故・病気・結婚・出産・親の介護・子どもの進学など、急にまとまった資金が必要になることは誰にでもあり得ます。しかしその際に解約しても、全額は戻ってこないのです。
さらに契約期間中は、毎月一定額の保険料を支払い続けなければなりません。
そのため、リストラや収入減、ライフステージの変化といった事情があっても、支払いを減額することはできません。
1年先の未来も分からないのに、10年以上資金を拘束される ― これは想像以上に大きなリスクです。
運用リスク
多くの人は「保険=安全・安心な商品」と捉えがちですが、実際には投資商品としての性質を持つ貯蓄型保険も多く存在します。
これが損失の大きな原因にもなっています。
保険料の一部または大部分が金融商品で運用されている
支払った保険料の全額または一部は、保険会社によって株式・債券・外貨預金などの金融商品で運用されます。
商品によっては運用リスクを保険会社が引き受ける(元本保証がある)ものもありますが、変額保険や外貨建て保険では契約者自身がリスクを負う「自己責任型の運用」になり、元本割れのリスクが非常に高いです。
運用コストが高くリターンが小さい
仮に運用がうまくいっても、信託報酬や保険会社への手数料が高く設定されているため、運用益が大きく削られます。
結果として、10年以上運用しても増えるのはわずか数%ということも少なくありません。
逆に、運用がうまくいかなければ大きな損失につながります。
投資知識がないまま契約すると危険
最大の問題は、こうした「投資商品としての保険」を、契約者が仕組みを理解せず“貯金感覚”で加入してしまうことです。
保険という名前が付いていても、その中身は複雑な金融商品であり、元本保証がないものや柔軟な運用変更が難しいものもあります。
つまり、金融知識が不十分なまま契約すれば、知らないうちにリスクの高い投資をしていたという事態になりかねません。
情報が不透明なリスク(ブラックボックス化)
さらに深刻なのは、契約者に提供される情報が極めて不明瞭な点です。
たとえば、変額保険や投資型の年金保険では、「アメリカの株式に分散投資している」「外国債券を中心に運用している」といったざっくりとした説明はされるものの、
- どの銘柄にどれだけ投資しているのか
- どの運用ファンドを使っているのか
- ファンドのリスク・リターン実績
といった具体的で定量的な情報はほとんど開示されません。
さらに、運用コストの内訳も非常に分かりにくいのが実情です。
- 信託報酬や保険会社の手数料が元本から引かれるのか、運用益からなのか
- 毎月差し引かれるのか、年1回なのか
- 手数料率が固定なのか変動なのか
こうした投資において重要な情報が説明されない、あるいは複雑すぎて理解困難なのです。
結果として、お金がどのように運用され、何からどれだけ引かれているのか等、中身が見えないまま保険料を払い続けるという、非常に不健全なブラックボックスのような構造になっています。
これは投資信託など他の金融商品と比べても透明性が著しく低いと言えるでしょう。
保険はついているが保障は薄い
元本保証型の商品であれば、「保険付き」という点でお得に感じる方もいるかもしれません。
確かに資金拘束リスクを除けば、死亡保険などが付いている分、一見魅力的に思えるかもしれません。
しかし、実際には保障内容が非常に薄いケースがほとんどです。
具体例
仮に一般的な貯蓄型保険を月6,000円の保険料で15年契約としてみましょう。
- 月6,000円の保険料を15年間支払い続けると、支払総額は約108万円
- 満期時に受け取れる金額は約100万円
- 死亡時に支払われる保険金額も100万円程度が一般的
生命保険に詳しい方なら分かると思いますが、この保険金額は非常に低額です。
他社の比較例(楽天生命)
今度は比較として、楽天生命の死亡保険である「スーパー定期保険」を見てみましょう。
- 30歳男性の場合 → 月980円(女性なら約710円)
- 死亡保険金 → 1,000万円
こちらは掛け捨て型ではありますが、
月6,000円払って100万円の保障と、月980円の保険料で1,000万円の保障では、保険料と保障額に圧倒的な差があることが分かります。
参考:死亡保険 楽天生命スーパー定期保険の保障内容|楽天生命保険:2025年8月20日現在
運用の観点から見た場合
保障だけを比べれば掛け捨て型がお得というのは分かりましたが、
「貯蓄型保険は保障と同時に貯蓄もできるからこそお得だ」という意見もあるかもしれません。
しかし実際には、資産運用をしながら掛け捨て保険に加入した方が、より効率的に保障と資産形成を両立できる可能性があります。
具体例で比較してみましょう
たとえば、元本保証型の貯蓄型保険に入れる100万円を 年利4%で15年間運用した場合、複利運用なら180万円以上になります。
同時に掛け捨て生命保険に加入すると・・・
- 100万円を年利4%で15年間運用 → 約180万円の運用益
- 月1,000円の掛け捨て生命保険(年間12,000円 → 15年で18万円)に加入
すると、最終的に手元に残るのは、
180万円 – 18万円 = 約162万円
つまり…
- 万が一のとき → 死亡保険金1,000万円
- 何もなければ → 162万円が手元に残る
このように、掛け捨て+資産運用の組み合わせの方が合理的になるケースもあり得ます。
当然、試算の仕方や運用利回りで結果は変わってきますが、ここ20年間の全米株式に分散投資するインデックスファンドの年平均利回りが8%〜10%前後であり、2025年8月現在の米国10年債の利回りは約4.2%前後であることを考えれば、リスクを抑えた運用でも年利4%は十分に現実的な数字と言えるでしょう。
そろばんをはじけば、元本保証型でさえ貯蓄型保険は非効率であることは明らかです。
ましてや、運用成績によって受取額が変動する変額保険などは、契約した時点で損をしていると考えるべきでしょう。
まとめ:貯蓄型保険はお得に見えて損している
貯蓄型保険には様々な種類がありますので、今回はザックリとした解説をしました。
貯蓄型保険は「保険+資産運用」を一つの商品にまとめることにより、お得なように見せていますが、実際には以下のような多くのリスクを抱えています。
- 元本割れリスク:特に途中解約時は大きく元本を割り込む可能性がある
- 資金拘束リスク:長期契約が前提となるため、必要なときにお金を自由に引き出せない
- 運用リスク:予定利率や運用実績によっては、損をしたり期待したリターンが得られない
- 機会損失リスク:満期で元本が戻ってきても、他の方法で得られたであろう利益を失う
結論としては、保障は保障、資産形成は資産形成で分けて検討するのが基本です。必要な保障は掛け捨てでシンプルに確保し、資産形成は流動性とコストを自分で把握できる手段で別管理する――このほうが柔軟で合理的になりやすいからです。
今後、各保険についての詳しい解説記事も掲載予定です。
ぜひほかの記事も見ていってください。
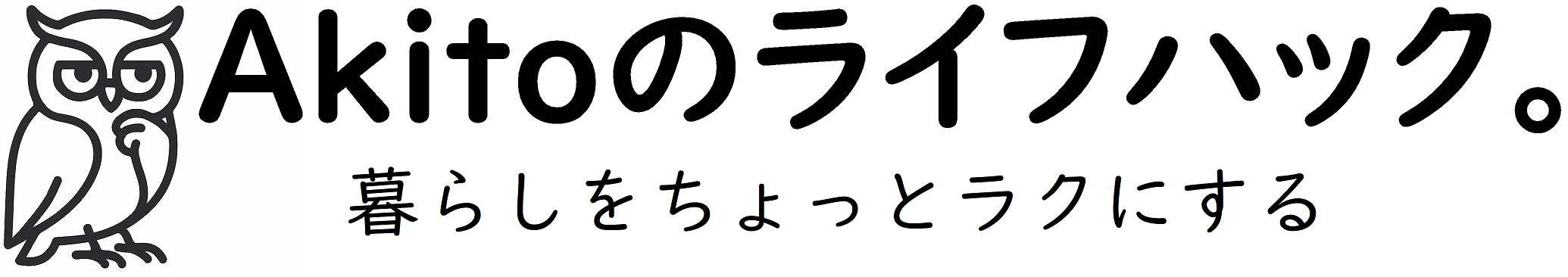



コメント