以前の記事で、資産運用の始め方と選ぶべき投資先について説明しました。
詳しくは下記を参照してください。
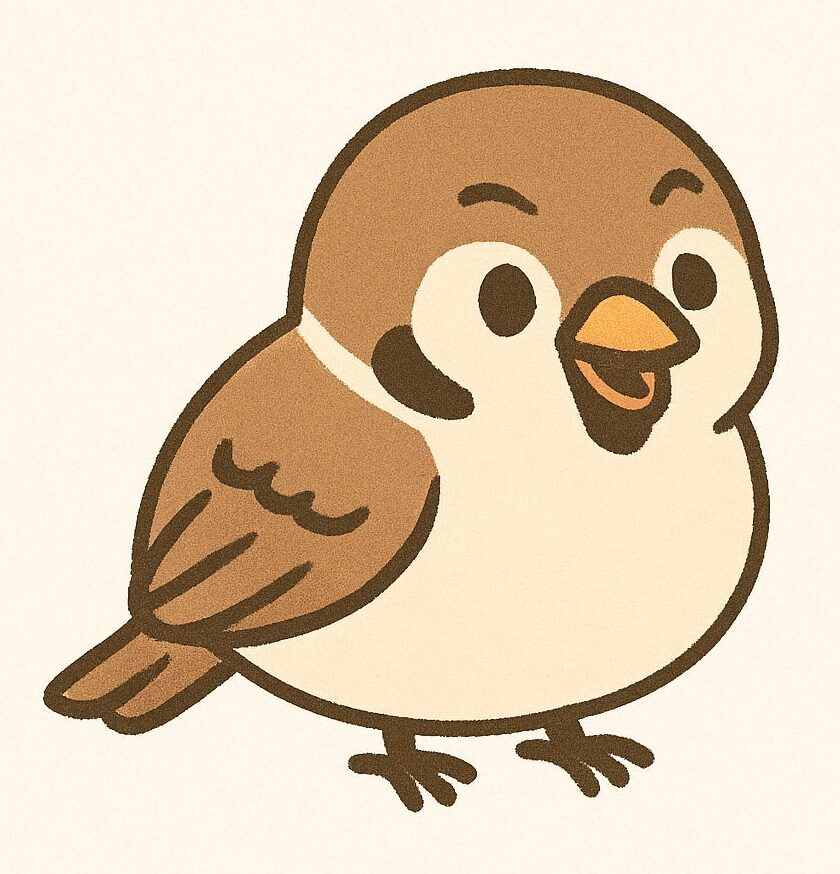
全米株式のS&P500とか、全世界株式のMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスの株価指数に連動しているインデックスファンドをおすすめしてるんだったよね。

長期的な資産運用という観点から見たとき、これらは非常に合理的で良い選択だからね。
- MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスに連動するインデックスファンド
例:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)など - S&P500に連動するインデックスファンド
例:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)など
今回は、これらの購入方法とおすすめの金融機関について解説していきたいと思います。
証券会社を選ぶ
当サイトでおすすめしているインデックスファンドをはじめ、投資信託や個別株、債券、ゴールドETFなどのペーパーアセットを購入するには、まず証券会社に口座を開設する必要があります。
そのため、どの証券会社で口座を開設するかを選びましょう。
おすすめの証券会社は以下の3社です。
SBI証券
国内最大級のネット証券で、取扱商品の幅広さは群を抜いています。加えて、三井住友NLカードを使った「カード積立」に対応しているのも魅力です。さらに、SBI証券+三井住友カード+住信SBIネット銀行という組み合わせは相性が良く、連携面でも非常に強力。操作性も安定しており、王道的な選択肢といえるでしょう。
三井住友NLゴールドカードにすれば、積立時のポイント還元は1%。当サイトおすすめのネット銀行である住信SBIネット銀行との連携も強力なため、特に理由がなければSBI証券を選ぶと良いでしょう。
楽天証券
楽天経済圏を活用している人には特におすすめです。楽天カード積立が利用できるうえ、楽天銀行との連携もスムーズ。楽天カード+楽天銀行+楽天証券という連携サービスが強みで、普段から楽天ポイントを活用している方にとっては、自然に投資を続けやすい環境が整っています。
ただし、これは私個人の意見ですが、楽天証券は過去に楽天カード積立のポイント還元率や株式保有ポイントなどの仕組みを度々改悪してきた経緯があるため、あまり好印象を持っていません。
詳しくは外部サイトですが、非常によくまとめられている記事を見つけましたので、参考までにリンクを貼っておきます。
とはいえ、他のネット証券と比較してもおすすめできる証券会社のひとつであることは確かです。
参考:【2025年版】楽天経済圏からの乗り換え先は?改悪の歴史と今後の選択肢を徹底検証|医師のポイ活道
マネックス証券
特筆すべきは、マネックスカードを使ったカード積立時のポイント還元率(1.1%)が高水準なことです(2025年9月現在)。年会費無料カードや比較的簡単な条件で得られる還元率としてはかなり高く、SBI証券(三井住友NLカード)や楽天証券(楽天カード積立)より有利になるケースもあります。
全体的な利便性や銀行との連携面ではSBI・楽天に劣る部分がありますが、「第3の選択肢」として検討する価値は十分にあります。
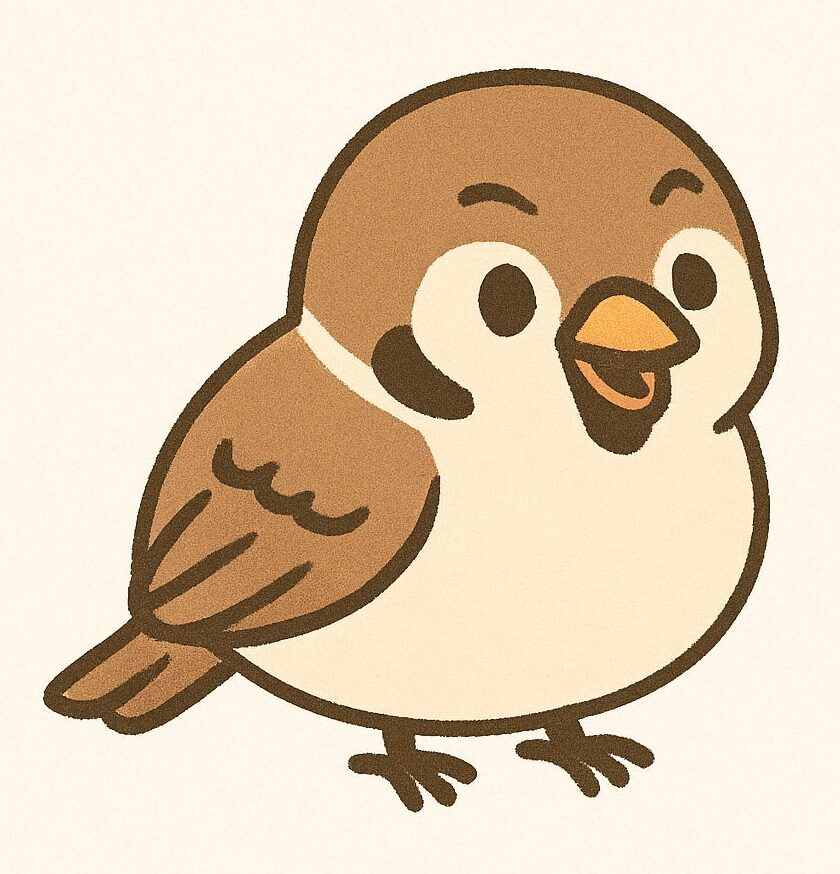
僕は楽天モバイルに楽天銀行、楽天カードを使ってるから、楽天証券にしよう。

僕は三井住友NLゴールドカードで積立ができるSBI証券にしました。自分の経済圏などを考慮して選ぶといいと思います。
NISA口座を開設しよう
どの証券会社でインデックスファンドを購入するか決めたら、まずはその証券会社で総合口座を開設しましょう。
基本的には、各証券会社のウェブサイトで「無料口座開設」などのボタンをクリックし、画面の指示に従って進めるだけで簡単に申し込みができます。
多くの場合、総合口座の開設と同時にNISA口座も申し込めますが、そうでない場合は総合口座開設後にNISA専用ページから別途申し込みを行いましょう。
NISA口座の開設が完了したら、各証券会社のNISAページで投資する銘柄と金額を選ぶだけで投資をスタートできます。
より詳しい手順は、各社が用意しているNISAの案内ページを参考にするのが分かりやすくておすすめです。
NISAは、少額からでも始められるのが大きなメリットです。
まずは月々数千円からでも積立投資をスタートしてみることをおすすめします。
NISAやiDeCoとは?
「資産運用」というテーマとセットで、NISAやiDeCoという言葉を耳にしたことがある人も多いと思います。
「NISAに投資する」「iDeCoをやる」といった言い方をよく聞きますが、これは厳密にいえば正確ではありません。
NISAやiDeCoは、株や投資信託などを購入・運用するための非課税制度付きの口座であり、投資商品そのものではないからです。
制度の詳細については、当ブログの以下の記事で解説していますので、興味のある方はぜひご覧ください。

口座開設はしたけど、投資するのがちょっと怖くなってきた……。

短期的には資産がマイナスになることもあるから、まずは自分の許容度の範囲内で小額から始めるのがおすすめだよ。資産運用はとにかく長期間続けることが大切なんだ。
おすすめしない金融機関
先ほど紹介した3社のネット証券以外でのNISAやiDeCoの利用は、当サイトでは基本的におすすめしません。
なぜなら、金融機関の多くは、実店舗や窓口を持ち、担当者による対面コンサルティングを行っているためです。
対面での相談やサービスは一見メリットに感じられますが、実際には店舗運営や担当者の人件費など、金融機関側に多大なコストがかかっています。
そのコストを回収するため、これらの対面販売を行う金融機関では、運用成績が良くないファンドや高額な手数料の「ぼったくりファンド」を勧められる可能性が非常に高いのです。
金融庁や消費者相談窓口でも、こうした「過剰な勧誘」や「高額手数料のファンドの販売」について繰り返し注意喚起がなされており、金融商品取引法に基づく規制も年々強化されています。
このような背景から、ネット証券以外の金融機関での資産運用は非常にリスクが高く、おすすめできません。
総合証券会社(店舗型証券会社)
総合証券会社は実店舗を構え、営業担当者が顧客につく対面型の証券会社です。
ネット証券が普及する前は唯一の選択肢でしたが、担当者を置き直接相談できる分、金融機関側のコストが非常に大きいのが現状です。
そのため、手数料の高いアクティブファンドを勧められ、結果的に高コストの商品を購入させられるケースが多いのです。
銀行
銀行でもNISAやiDeCoを扱うことがありますが、地銀やメガバンクの窓口はおすすめできません。
銀行は証券会社ではないため、取り扱うファンドの種類が限定的で、手数料が高い商品が多い傾向にあります。
また、銀行の窓口販売は対面勧誘が中心で、やはり高額手数料のアクティブファンドをすすめられやすいのが実態です。
ネット証券と比較すると、利便性の面でも大きく劣ります。
当サイトでは、そもそも地銀やメガバンクなどの店舗型銀行は理由がない限り利用しないことを推奨しています。
関連記事:
その他金融機関(郵便局・信用金庫・信託銀行など)
郵便局や信用金庫、信託銀行も基本的には銀行と同様です。
- 扱うファンドの種類は限られている
- 手数料の高い商品が多い
- 利便性も低い
- 高コストなアクティブファンドを勧められやすい
結果として、ネット証券で購入できる商品に比べて運用成績が劣る傾向があるため避けるべきです。
SBI、楽天、マネックス証券以外のネット証券
ネット証券には、SBI証券・楽天証券・マネックス証券以外にも、ネット証券はたくさん存在しています。
多くのネット証券は上記の対面型の金融機関に比べれば、非常に良い選択になりますが、当ブログでは、特におすすめはしていません。
理由はシンプルで、おすすめする明確なメリットが見当たらないからです。
たとえば、他のネット証券をすでに使い慣れているなど、個人的な理由があれば利用しても問題ありません。
ただし、カード積立によるポイント還元率、銀行との連携、各社の経済圏との相性などを総合的に比較したとき、特段優れているポイントがないため、積極的に推す理由がないという判断です。

利便性、リスク、コストどれをとっても基本的にはネット証券が優れているんです。
まとめ:資産運用を始めるためにやるべきこと
今回の記事では、資産運用を始めるための具体的な第一歩について解説しました。
やるべきことの再確認
- 投資先を選ぶ:S&P500や全世界株式(オルカン)に連動する低コストのインデックスファンドがおすすめ
- 証券会社を選ぶ:ネット証券の利用が圧倒的に有利。特にSBI証券・楽天証券・マネックス証券はサービスが充実
- NISA口座を開設する:投資で得た利益が非課税になる制度。まずは少額から積立を始めてみましょう
資産運用は「続けること」が成功の鍵
投資を始めたばかりの頃は、株価の変動に一喜一憂してしまうかもしれません。
しかし、資産運用は15年、20年という長期目線で行うものです。
最も大切なことは、長期的に続けることです。
例えば、毎月3万円を20年間積み立てると、元本は720万円。
もし年平均5%で運用できれば、約1,200万円にまで増える計算になります。
短期的には損をすることもあるため、株価が下がっても売らずにコツコツ積み立てを続けることが成功の秘訣です。
次回は、投資すべきでない金融商品について解説します。
当ブログでは暮らしをより良くするための情報を発信していますので、ぜひ他の記事もご覧ください。
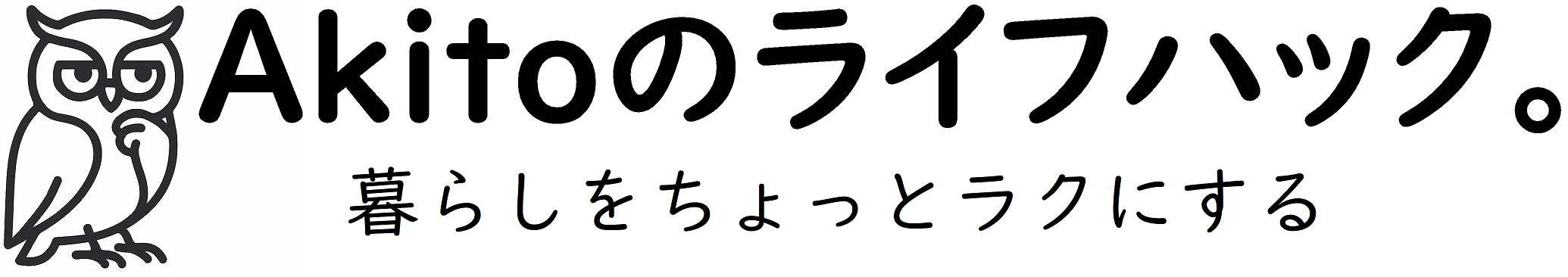



コメント