こんにちは、Akitoです。
引っ越しの際、最後に待っているのが「退去費用」。
「え、こんなに請求されるの?」と驚いた経験はありませんか?
以前の記事でもお話ししましたが、不動産業界には悪質な業者が非常に多いのが実情です。
賃貸では入居時にもぼったくりが多いですが、退去時にも不当な費用を請求されるケースが多々あります。
知らずに支払ってしまえば、数万円〜10万円以上の損になることもあります。
今回は、不当な退去費用の実態と、防止策・対処法をわかりやすく解説します。

「不動産投資にしろ、賃貸にしろ、不動産業界は不正やぼったくりが非常に多いです。この記事で一緒に勉強していきましょう。」
前提として、借主は「原状回復義務」を負う
勘違いしてほしくないのは、すべての退去費用が不当な請求ではないという点です。
借主は、借りた物件を大切に扱う義務があり、退去時には入居時と同じ状態に戻す責任を負います。
これを「原状回復義務」といいます。

「当然、部屋を傷つけたり汚したりした場合は、修繕費用を払わなければなりません。
ただし、払わなくても良いものを請求されるケースもあるため注意が必要です。」
国土交通省のガイドラインの考え方
しかし実際には、原状回復で借主が負担する範囲は限られています。
国土交通省が示す「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、
借主が負担すべきなのは 「故意や過失による損傷」 のみです。
つまり、壁紙の色あせや日常使用による汚れなどは「経年劣化」とされ、借主の負担にはなりません。
NG例(借主負担)
- 壁の傷
- タバコの焦げ穴
- 子どもの落書き
- 物を落とした床のへこみ
OK例(貸主負担)
- 壁の小さな画鋲穴
- 家具の設置跡
- 日常使用による汚れ

「家具の跡や画鋲の穴など、意外と原状回復義務がない項目も多いんです。
詳しくは国交省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』を読んでおくと良いでしょう。」
修繕費用は新品価格ではない
もしあなたが今の物件に長く住んでいた場合や、物件自体の築年数が古い場合、故意・過失による汚損や破損であっても、支払い義務がない、もしくは大幅に安くなる可能性があります。
壁紙や床などの設備には、使用できる期間を示す「耐用年数」が定められています。主な設備の耐用年数は以下の通りです。
| 設備 | 耐用年数 |
|---|---|
| 壁紙(クロス) | 6年 |
| 床(クッションフロア) | 6年 |
| エアコン・給湯器・ガス機器等 | 6年 |
| 便器・洗面台など | 15年 |
| 床(フローリング) | 経過年数を考慮しない場合が多いが、建物の耐用年数(例:木造22年)で計算されることもある |
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、借主が原状回復費用を負担する場合、新品価格ではなく、経過年数を考慮した残存価値に基づいて計算するとされています。
たとえば、耐用年数6年の壁紙を4年間使用した場合、すべて借主負担で張り替えるのは不当です。
実際は、残りの2年分(約33%)のみを負担するのが妥当とされています。
(借主の負担割合 =(耐用年数6年 − 経過年数4年) ÷ 耐用年数6年 × 100% = 約33%)

「こう見ると理屈上は耐用年数を超えていれば、どれだけ汚してもよさそうに見えますが、悪質なケースでは支払い義務が生じることがあります。絶対に故意に設備を傷つけたり汚したりしてはいけません。」
適用範囲は汚損・破損部分のみ
借主が原状回復義務を負うのは、修繕が必要となった部分のみです。
壁紙の一部を汚してしまった場合は、その汚れが付いた壁紙1枚分のみが対象となります。
しかし、悪徳不動産業者は、平然と壁一面や部屋全体の張り替え費用を請求してくることもあるため注意が必要です。
火災保険で修繕費用をカバーできる場合がある
多くの賃貸契約では、火災保険の加入が義務付けられています。
実はこの火災保険には「修理費用補償」や「破損・汚損損害等補償特約」といった補償が含まれている場合があります。
これを利用すれば、自分の過失による破損でも費用をカバーできる可能性があります。
たとえば、以下のようなケースです。
- 飲み物をこぼして床にシミを作ってしまった
- 家具をぶつけて壁に穴をあけてしまった
- 子どもが壁紙に落書きをしてしまった
- 室内設備を誤って壊してしまった
このような場合、本来は退去時に自己負担となる修繕費でも、火災保険から支払える可能性があります。

補償範囲は保険会社や契約内容によって異なります。一度、自分の火災保険の内容を確認しておくとよいでしょう。意外と、保険でまかなえるケースは少なくありません。
退去費用を高くしてしまう「特約」の存在
退去時に借主が負担すべき費用は、基本的に国交省のガイドラインで定められています。
しかし、本来は借主に支払い義務がない項目でも、支払い義務が生じる場合があります。
その理由は契約時に知らず知らずのうちに「特約」が結ばれていることがあるためです。
特約とは?
「特約」とは、法律上は借主に負担義務がない費用を、特別な約束によって借主負担とするものです。
よくある特約の例は以下の通りです。
- ハウスクリーニング特約:本来は貸主負担のクリーニング費用を借主に請求
- 鍵交換費用の特約:退去時の鍵交換費を借主に負担させる
- 通常損耗・経年劣化も借主負担とする特約:壁の色褪せ等、通常損耗・経年劣化まで借主に負担させる。
- 短期解約時の違約金特約:契約期間途中で解約した場合に家賃1〜2か月分を請求
特約が有効となる条件
すべての特約が有効とは限りません。
有効と認められるためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 特約に合理的な必要性があること
- 借主が内容を十分に理解していること
- 借主がその負担に同意していること
たとえば、特約が契約書の別ページにこっそり記載されていた場合や、重要事項説明がなかった場合は、無効になる可能性があります。
また、消費者契約法に照らして不当と判断されるケースもあります。
有効・無効の判断は個別の事情によって異なるため、国民生活センターや消費生活センターなどの専門機関に相談するのがおすすめです。

「なんかよくわかんなくて、いつも適当にサインしてたけど、それじゃダメなんだね。」

「そうだよ。トラブルを避けるためにも、契約時に特約はしっかり確認しておこう!」
不当請求を防ぐために
悪質な不動産業者は、知識のない借主を狙って特約にすらない本来払う必要のない費用を請求してくることがあります。
しかし、事前の対策でトラブルを防ぐことが可能です。
以下のポイントを押さえましょう。
退去前に部屋の写真を撮る
入居時の写真があれば理想ですが、多くの人は残していません。
それでも、退去直前に部屋全体を撮影しておくことをおすすめします。
悪質な業者は、退去時にはなかった傷や汚れまで請求してくることがあるためです。
退去時は立ち会わないほうがよい
一般的には退去時に立ち会い、鍵を返却するケースが多いですが、不当請求を避けるためには立ち会いを控えたほうが安全です。
立ち会い時に不当な費用を請求し、「サインをしないと退去できない」などと強要されるケースがあるためです。
実は、退去は電話やメールで意思を伝え、鍵を郵送するだけで成立します。
しかし、管理会社によっては立ち会いを必須とし、高額な費用を請求してくることがあります。
一度サインしてしまうと、修繕費用の支払いに同意したとみなされ、不当な請求に応じざるを得なくなる恐れがあります。
可能であれば、メールで退去の意思と日程を伝え、鍵は郵送で返却し、請求がある場合は請求書の送付を依頼しましょう。

「悪質な業者は不当な請求のサインを強要します。立ち合いは必須ではないので、特に女性の一人暮らしなどの場合は、立ち会わずに鍵を郵送したほうが安心です。」

「こわっ!良心的な業者もいるけど、不動産業界は悪質なケースも多いから注意しないとね……。」
不当な請求が届いたら
退去後に請求書が届いたら、まずは内容を冷静に確認しましょう。
請求項目や金額に納得できない場合、すぐに支払う必要はありません。
たとえば「ハウスクリーニング費用」などは、契約時に特約が結ばれていれば借主負担となる場合があります。
ただし、以下のような場合は特約が無効とされる可能性があります。
- 特約が契約書の借主サインとは別ページに記載されている
- 費用の金額や負担内容が不明確
- 宅建士から口頭での説明がなかった
- 相場に対して著しく高額な請求内容である
実際に、こうした条件を満たさず「ハウスクリーニング特約」が無効と判断された裁判例もあります。
つまり、「特約がある=必ず支払うべき」というわけではありません。
対応の仕方
疑わしい特約がある場合は、管理会社に以下のようにメールで伝えましょう。

「この特約の有効性に疑問があるため、無効にしてください。」
それでも請求を強く求められる場合は、次のように対応します。

「専門家に確認しますので、この特約の法的根拠と有効性を示してください。」
正当な請求であれば、管理会社は根拠を示せるはずです。
納得できないまま支払うのではなく、消費者センターや弁護士に相談することが重要です。
参考:
ハウスクリーニング特約拒否で賃貸退去費用を減額!判例と弁護士直伝2025年最新版|ハウスケアラボ
「曖昧な請求書」には内訳の提示を求める
「壁紙張り替え」「修繕費用一式」など、内訳が不明確な請求には注意が必要です。
修繕費は、故意・過失による損傷箇所のみが対象です。
そのため、明細が不明な請求が届いた場合は、次のように依頼しましょう。

「修繕箇所とその費用の明細を出してください。」
また、特約も存在しないのにクリーニング費用や経年劣化部分の修繕費が請求されていた場合は、支払いを明確に拒否できます。

「これは国土交通省のガイドラインで借主負担ではないとされていますので、支払いには応じません。」
特約もない不当な請求の場合、ほとんどの業者はこれで引き下がりますが、中には“ガイドラインに法的拘束力はありません”などと言ってくる業者もいます。
しかし、実際の裁判ではガイドラインが基準として扱われるため、実質的に強い効力を持ちます。
悪徳不動産業者は平然と嘘をつくため、言いくるめられないように注意しましょう。
まとめ
不動産業界にはこのように不当な請求をする悪徳業者が後を絶ちません。
こちらが正当な根拠を示しても、なお請求を続けてくる場合や、自分に支払い義務があるのか判断に迷う場合は、以下の専門機関に相談しましょう。
- 国民生活センター
- 消費生活センター(自治体窓口)
- 法テラス(無料相談窓口あり)
- 弁護士(無料相談制度が利用できる場合あり)
あなたに本当に支払い義務がなければ、請求は取り下げられるでしょう。
判断が難しいケースでは、専門家のアドバイスを受けることが大切です。
- 不明確な請求には、内訳や根拠を求める
- 不当な特約には、無効を主張できる
- ガイドラインに基づき支払いを拒否できる
- 必要に応じて専門機関へ相談する
請求が正当か不当かを判断するためにも、すぐにサインや支払いをしてはいけません。
「言われたから払う」ではなく、「確認してから払う」姿勢を徹底しましょう。
当ブログでは他にも生活に役立つ情報を発信していますので、ぜひ他の記事もチェックしていってください。
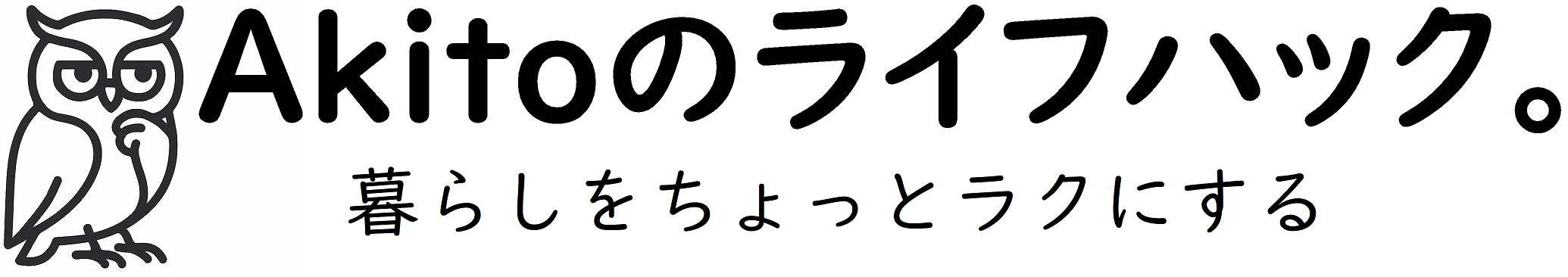



コメント