最近、NISAと並んで「iDeCo」という言葉を耳にする機会が増えてきました。
けれども、「名前は知っているけれど、具体的にどんな制度なのか分からない」という人も多いかもしれません。
今回は資産運用に役立つiDeCoについて簡単に解説していきます。
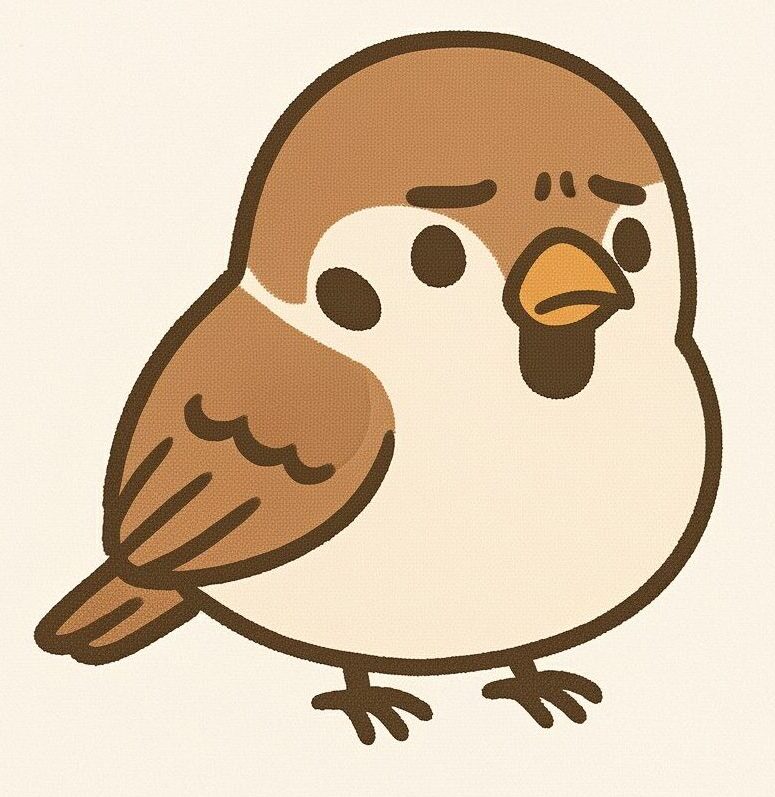
銀行とかでNISAと並んでよく見るけど、結局何なのか僕も知らないな……。
iDeCoとは?
iDeCoは “individual-type Defined Contribution pension plan” の略称で、日本語では「個人型確定拠出年金」と呼ばれます。
名称のとおり、国民年金や厚生年金と並ぶ「年金制度の一つ」なのです。
もともと年金には国民年金と厚生年金の2つがあり、すべての国民が加入する国民年金と、それに加えて会社員や公務員が加入する厚生年金があり、「2階建て」と呼ばれる仕組みになっていました。
1. 国民年金
国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人に加入が義務付けられている年金制度です。
自営業者や学生、無職の人などは、国民年金に加入して自分で保険料を納めます。一方、会社員や公務員の方は、勤め先で加入する厚生年金に国民年金も含まれているので、あらためて国民年金の保険料を払う必要はありません。
また、会社員や公務員の配偶者で扶養に入っている方は、保険料を払わなくても65歳から年金を受給できます。
2. 厚生年金
ほとんどの会社員や公務員は、必ず厚生年金に加入します。実は、パートやアルバイトの方でも、週の労働時間が20時間以上など、いくつかの条件を満たせば加入が義務付けられています。
厚生年金に加入すると、国民年金に加えてさらに厚生年金分も保険料を払うことになります。その分、将来受け取れる年金額が増えるので、老後の生活がより安心なものになります。
この2つの年金制度に加えて、任意で加入できる「第3の年金制度」として位置づけられているのがiDeCoです。
公的年金(国民年金・厚生年金)は加入が義務付けられています。
自営業者などは自分で納付しなければならず、未納の場合は督促状が届きます。
一方、会社員や公務員は給料から自動的に天引きされるため、「払っている感覚」が薄い人もいるかもしれません。
これに対してiDeCoは、加入が義務ではなく、自分の意思で選んで積み立てる「任意の年金制度」 となっています。
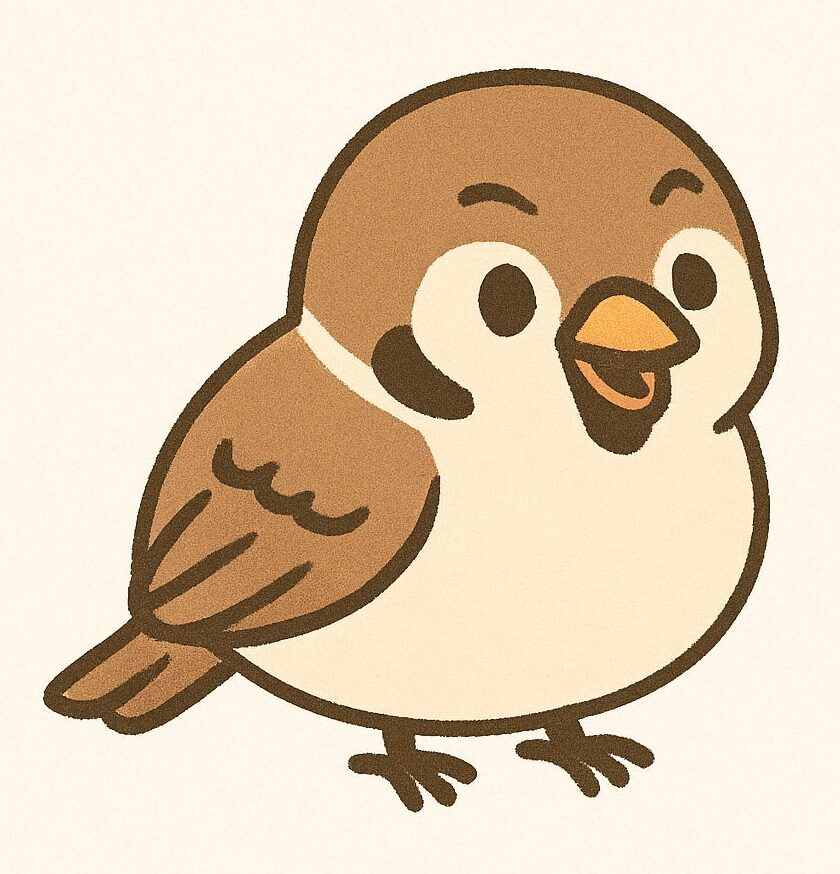
年金の一つなんだね!でもなんで3つも年金が必要なの?

iDeCoには公的年金にはない特徴やメリットがあるんだ。次のパートで詳しく見ていこう。
iDeCoの特徴・メリット
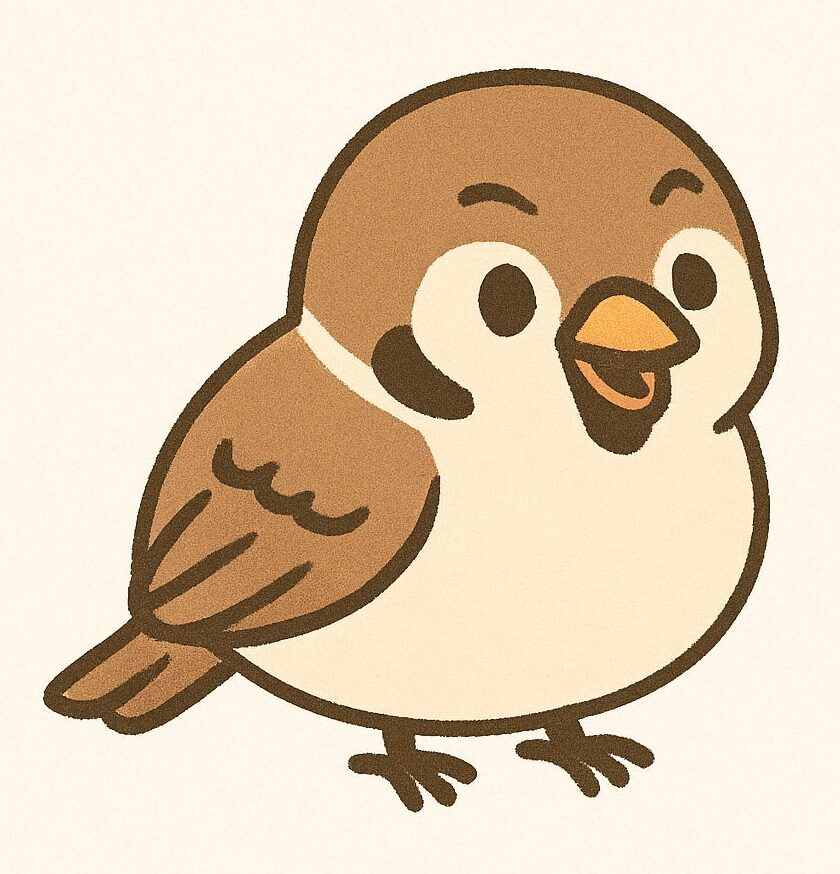
iDeCoが年金だってことは分かったけど、他の年金とどう違うの?

iDeCoの最大の特徴は、自分の年金を自分のお金で積み立てて準備し、さらにそのお金を運用できるってところなんだ。
積み立て方式
国民年金や厚生年金は「賦課方式(世代間扶養)」と呼ばれ、「積み立て方式」ではなく、現役世代が払った保険料をその時の高齢者に支払う構造になっています。
自分の支払ったお金は今の高齢者に年金として支払われているのです。
現在は少子高齢化が進んでいるため、「自分が支払った年金額よりも受け取る年金の方が少ないのではないか」という懸念から、「年金なんてもらえるかどうかわからない」という人が多いのです。
そんな賛否両論ある年金制度ですが、iDeCoの場合は「積み立て方式」のため、支払ったお金はすべて自分のお金として受け取ることができます。
積立金を運用できる
iDeCoで積み立てたお金は、自分で選んだ金融商品で運用して増やすことができます。
つまり、iDeCoで積み立てたお金を、決められた中から投資に回せるということです。
投資というと怖いイメージがあるかもしれませんが、法律や厚生労働省のガイドラインに基づき運用商品は選定されており、極端にリスクの高い商品は除外されています。
詳しいことは資産運用に関する記事で説明していますが、当サイトでは基本的にはインデックスファンドをおすすめします。
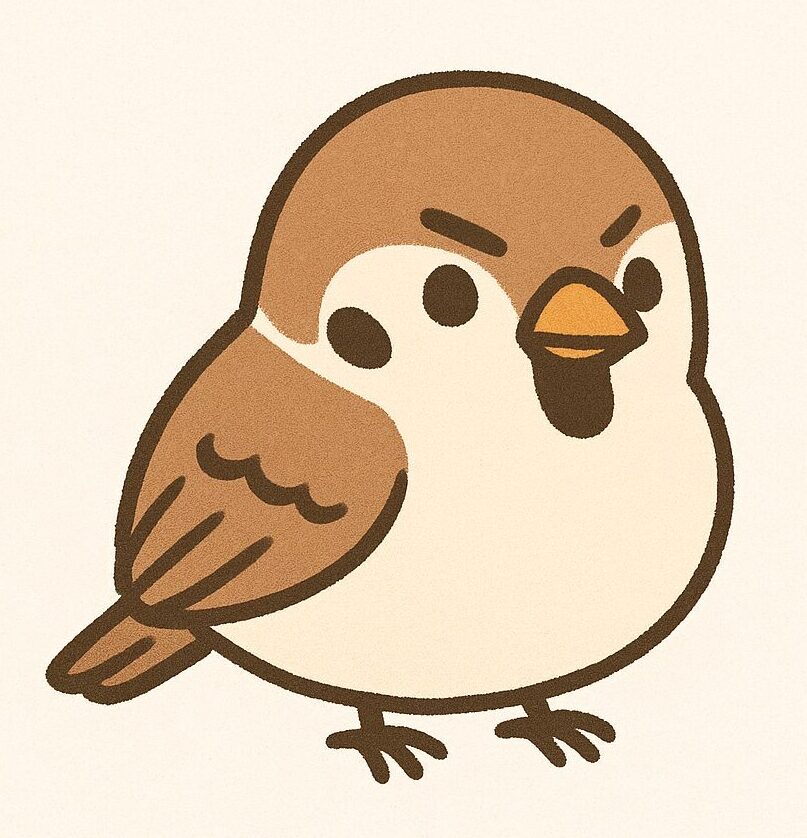
なるほど、自分で積み立てて運用できる年金ってことなんだね。

その通り。そういう意味でiDeCoは他の年金制度とは大きく違うよね。そのうえで、下記のようなメリットもあるんだ。
所得控除による節税効果
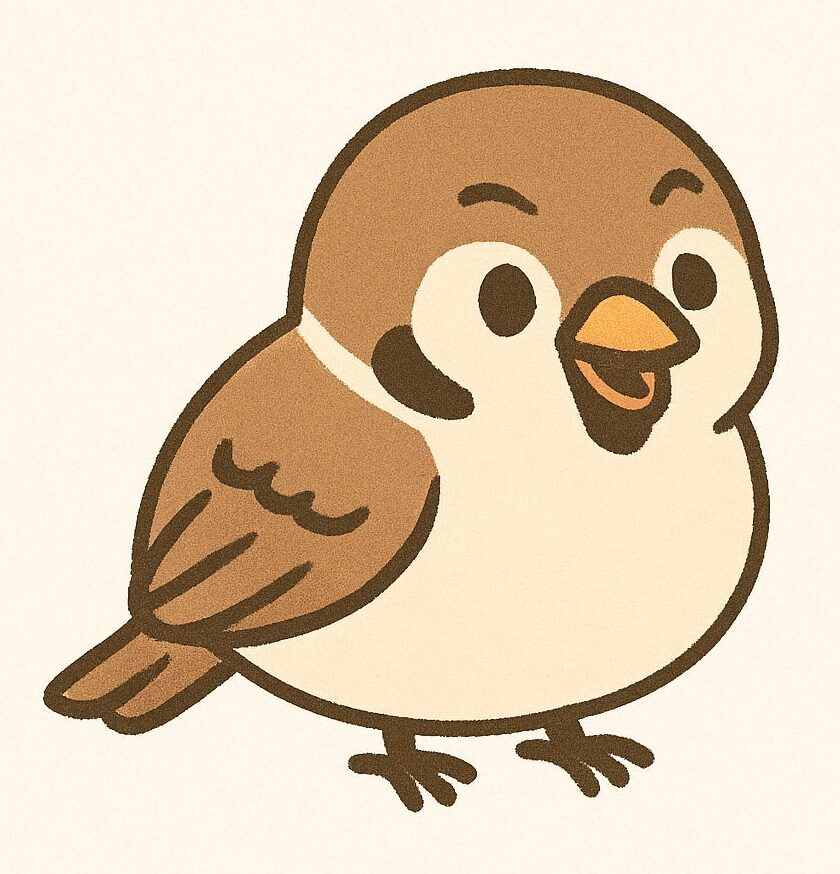
年金で節税ってどういうこと?
毎月積み立てたお金は、そのまま全額が「所得控除」の対象になります。
例えば、毎月2万円、年間で24万円をiDeCoに積み立てた場合、その24万円分の収入が「なかったこと」として計算され、払う税金が少なくなります。
年末調整や確定申告で控除として申告すれば、所得税や住民税が安くなるので、実質的に 「お金を貯めながら節税もできる」 という一石二鳥の制度です。
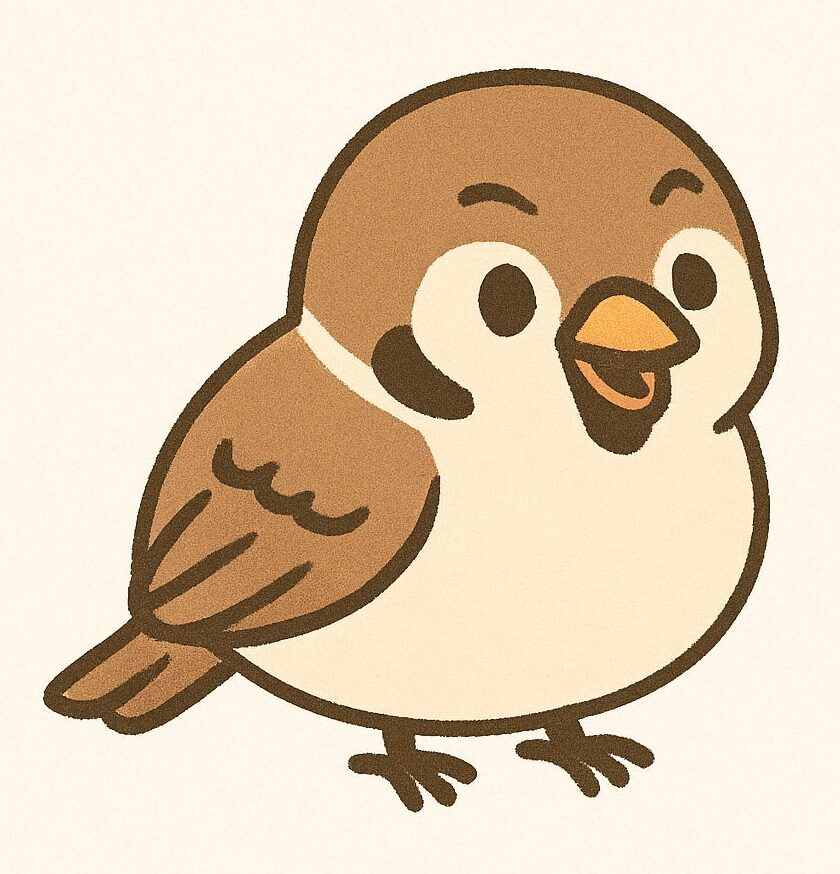
積み立てた分が所得控除になって税金まで安くなるなんてすごくお得!

まさに一石二鳥の制度と言えますね。
運用益が非課税
通常、株式や投資信託などで利益が出ると、その約20%は税金として引かれてしまいます。
たとえば、10万円儲かっても2万円は税金として取られてしまうということです。
でも、iDeCoで運用して得た利益には税金が一切かかりません。
利益がどれだけ出ても、まるごと全部自分の資産になるというのが大きな魅力です。
長期間にわたって積み立てていくiDeCoでは、少しずつの利益でも非課税効果によって将来的に大きな差がついてくる可能性があります。
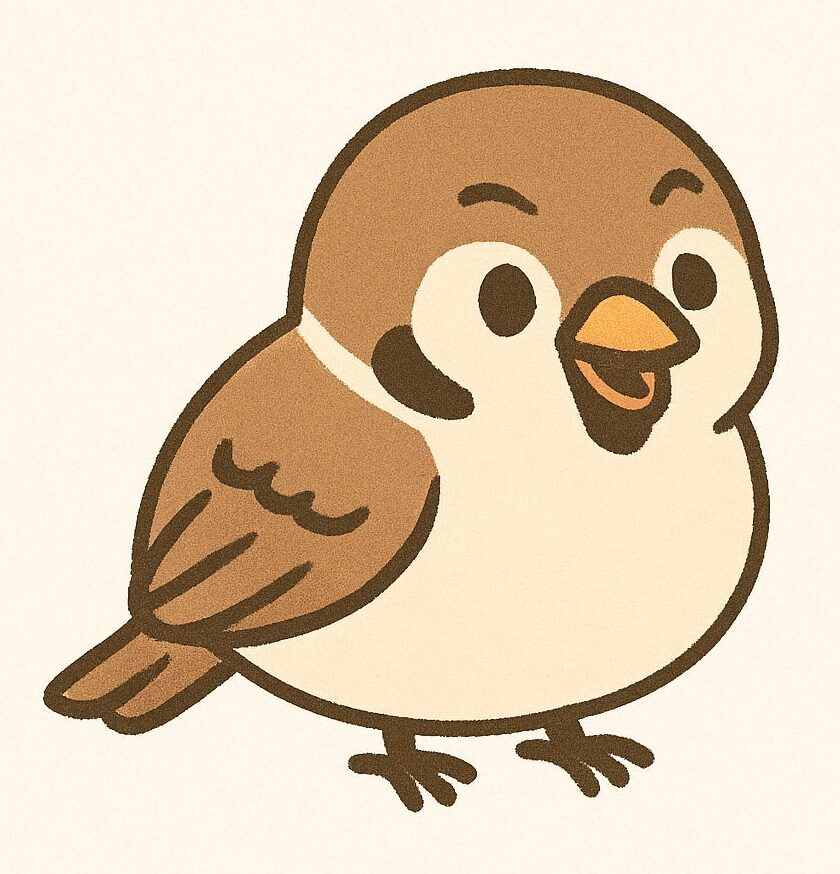
NISAと同じで非課税なのはすごくお得だね!

積み立てが終わり受け取るときには金額が大きくなっているはずですので、20%というのは想像以上に大金です。それがそのまま非課税なのは大きなメリットですね。
受取時の税制優遇
iDeCoで積み立てたお金は、60歳以降に「一時金」または「年金」として受け取ることになります。
この受け取り時にも税金の優遇措置があります。
- 一時金としてまとめて受け取る場合 → 「退職所得控除」が使えます。退職金と同じ扱いで、勤続年数に応じて控除枠があり、一定額まで非課税になります。
- 年金のように分割して受け取る場合 → 「公的年金等控除」が使えます。国民年金や厚生年金と同様に、一定額まで非課税になります。
iDeCoが他の年金と異なるポイントは、一時金・年金形式のどちらでも受け取れる「選択肢」があることです。
自分の状況に合わせて年金として定期的に受け取ることも、退職金として一度に受け取ることもできるのは、iDeCoの大きなメリットです。
iDeCoのデメリット
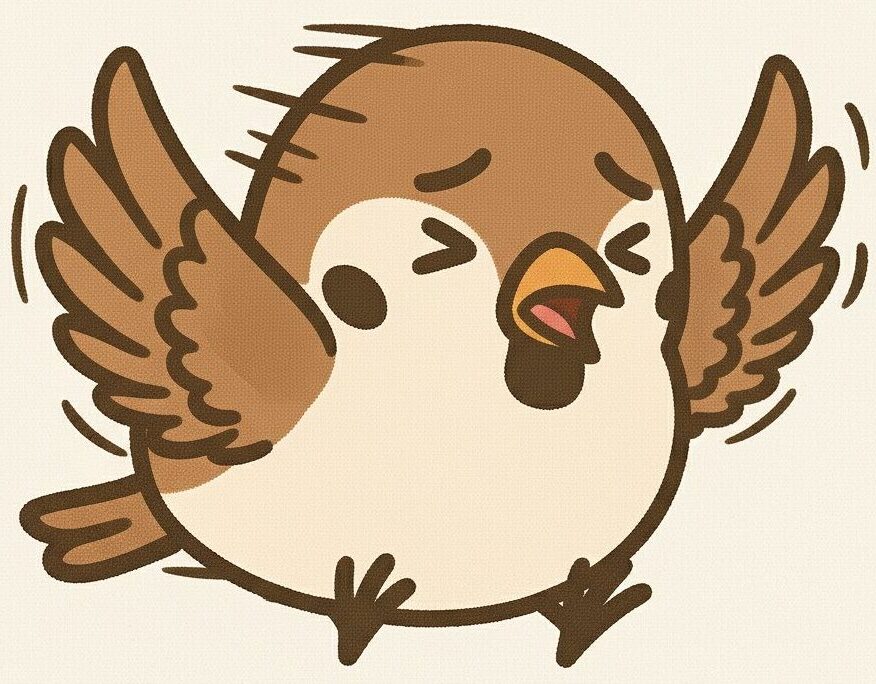
こんなにお得なんだからすぐに始めなきゃ!💦

ちょっと待って!iDeCoにもデメリットはあるから、ちゃんと理解してから検討しよう!
60歳まで引き出せない
iDeCoの最大のデメリットは、原則60歳まで引き出せないことです。
iDeCoは年金制度の一つという特性上、60歳になるまで引き出すことができません。
そのため、緊急時の資金としては使えないのです。
特に若い世代にとっては60歳などずいぶん先の話ですし、本当に「年金」として払っているという意識で、余裕資金の範囲内でiDeCoで積み立てるべきでしょう。

いざとなっても60歳までは引き出せないので、他でしっかり資産運用をしたうえで、余剰資金で積み立てることをお勧めします。

資金拘束されるから確実に積み立てはできそうだけど、緊急時に手元にお金がないのは困るかも……。
口座管理手数料がかかる
iDeCo同様、資産運用ができる制度であるNISAでは、インデックスファンドを購入すれば基本的には信託報酬しか手数料はかかりません。
しかし、iDeCoでは信託報酬のほかに下記の手数料がかかります。
- 加入時に払う手数料
加入・移転時に国民年金基金連合会へ2,829円の支払い - 積立手数料
掛け金の納付があるたびに国民年金基金連合会へ105円の支払い(掛金収納手数料) - 口座手数料
運営管理機関(証券会社や銀行など)へ毎月の口座管理手数料を支払う。多くは月約171円で、数十円から数百円まで各金融機関で異なる。
補足:2025年9月現在、ほとんどのネット証券では無償化されました。 - 受取事務手数料
年金または一時金受取の際に事務手数料(数百円)がかかる。
いずれも高額ではありませんが、毎月かかる手数料もあるため、30年などの長期で見るとそれなりの額になります。
参考:https://www.ideco-koushiki.jp/library/|iDeCoのご案内:iDeCo公式サイト
※インデックスファンドとは、投資信託のうち特定の株価指数に連動することを目指して運用されるファンドです。
※信託報酬とは、投資信託(ファンド)の運用会社・販売会社・信託銀行などに分配される手数料です。
当サイトがおすすめしているeMaxis Slim 全世界株式、および全米株式(S&P500)などでは、いずれも0.1%未満となっています。
確定申告が必要な場合もある
iDeCoの掛け金は「全額所得控除」の対象ですが、その控除を反映させるには手続きが必要です。
特に自営業者は毎年の確定申告で自分で申告しなければ、節税効果を受けられません。
また、会社員でも勤務先がiDeCoの掛け金を年末調整に反映してくれないケースがあり、その場合は自分で確定申告を行う必要があります。
手続き自体は難しくなく、「小規模企業共済等掛金控除」として申告書に記入すればOKですが、申告を忘れると節税メリットがゼロになってしまうため要注意です。
今後、制度が改悪される可能性も
2025年度の税制改正では、iDeCoの「受取時の税制優遇」に重要な変更がありました。この改正は、2027年以降に受け取る退職金等に適用される見込みです。
これまで、退職金とiDeCoの一時金を5年以上空けて受け取れば、それぞれに退職所得控除を個別に適用できていました。
しかし改正後は、この「5年ルール」が「10年ルール」に変更され、受け取り間隔が10年未満の場合は控除が通算されることになりました。
例:
- 60歳で会社の退職金を受け取り
- 65歳でiDeCoの一時金を受け取った
従来は別々に退職所得控除が使えましたが、今後は合算扱いとなり、控除枠を超えた分に課税される可能性があります。
必ず課税されるわけではありませんが、退職金が多い人ほど課税リスクは高まるため注意が必要です。
iDeCoの一時金を確実に別枠の控除で非課税にしたい場合は、退職金の受け取りから10年以上空けて受け取る必要があります(例:70歳以降など)。
この改正で注目すべきなのは「資金拘束される制度に縛られたまま、後からルールが変わるリスクがある」という点です。
iDeCoは原則として60歳まで引き出せない資金拘束型の制度。にもかかわらず、途中で不利な制度改正がされても、資金を戻すことはできません。
今回のような制度変更は、iDeCoを長期で利用している人にとって、信頼性を揺るがす出来事だったと言えるでしょう。

え!?じゃあ極論、やっぱ税金めっちゃ取りまーす!とかもあるの……?

さすがにそこまで極端なことはないと思うけど、そう不安になっちゃう人がいるのも無理はないよね……。
まとめ:お得な制度だけど注意が必要
2025年の制度改正で改悪された現在も、iDeCoは依然として非常にお得な制度であることに変わりはありません。
非課税で資産運用ができ、老後資金を効率的に準備できます。
ただし、NISAと比べるとiDeCoには以下の注意点があります。
- 60歳まで資金が引き出せない「資金拘束」がある
- 複数の手数料が発生する
- 受け取り方によっては課税される可能性がある
- 制度がやや複雑で分かりづらい
さらに、iDeCoは一度制度改悪された過去があるため、将来も同様の変更がないとは言い切れません。
加入対象が拡大など、以前には利用者にとって良い改正もありました。しかし、資金拘束される制度なのにも関わらず後から制度改正をされてしまうというのは大きな問題です。
「良い制度だと思って長期間積み立て続けていたのに、気づけば全然お得じゃなくなっていた」という事態もあり得るのです。
制度をころころ変えるため、複雑で分かりづらくなってしまっているのも大きな問題です。
資産運用や老後資金の準備という点では、まずはNISAを活用するのが基本戦略です。
そのうえで資金に余裕がある人は、iDeCoを“補助的に”活用するのがよいでしょう。
NISAや資産運用に関する他の記事も書いています。
少しでも皆さんの生活をラクにできる情報を発信していきますので、ぜひ他の記事もご覧ください。
関連記事:
資産運用って何?将来のためにあなたができること【その1】資産運用とは
資産運用って何?将来のためにあなたができること【その2】資産運用に選ぶべき投資先は?
新NISAとは?仕組み・メリットを初心者向けにわかりやすく解説|今さら聞けないシリーズ【その1】
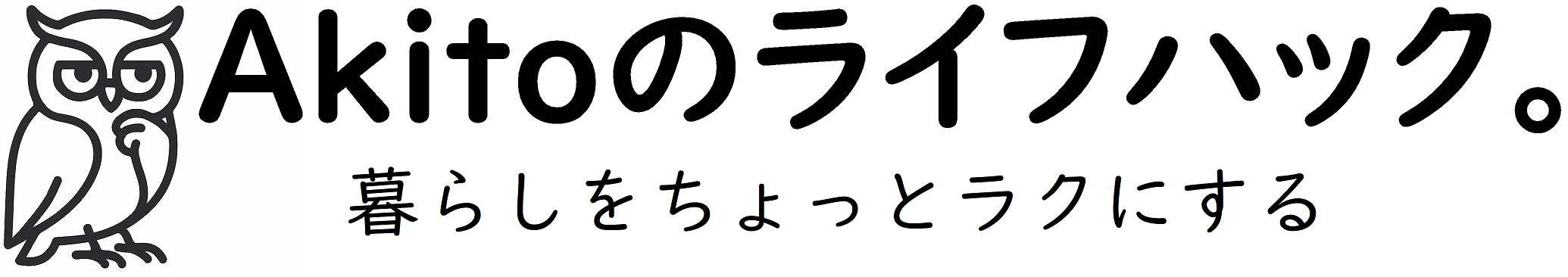
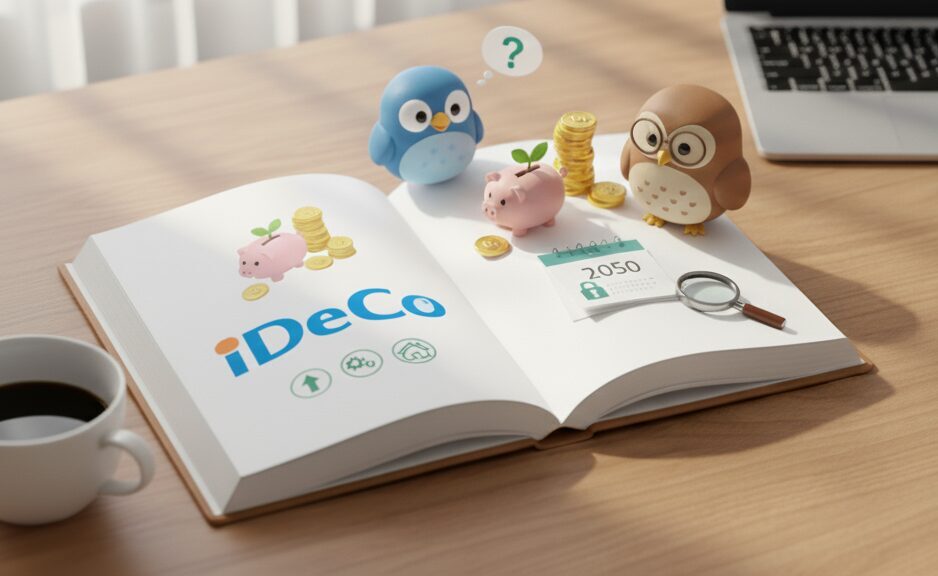


コメント